
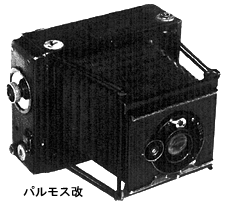 写真の世界、学生でもアマチュアでも、若い人たちは難しい言葉をつかいたがる。聞き慣れない専門用語ををつかうことでちょっとした優越感が味わえるからだろう。写真学校でも新学期がはじまって、一月、二月たつと学生たちの会話にやたら難しい言葉が入ってくる。被写界深度、相反則不軌、色温度、寛容度といった種類の技術的な用語と、マニピュレーテッド・フォトとかトポグラフィックスのような写真の表現や主義についての言葉だ。こんな言葉のなかで技術用語は写真を写すためには、知っていても知らなくても直接関係ないように思われる言葉だが、内容はいずれもよい写真を撮るためにはどうしても知っていないと困ることである。
写真の世界、学生でもアマチュアでも、若い人たちは難しい言葉をつかいたがる。聞き慣れない専門用語ををつかうことでちょっとした優越感が味わえるからだろう。写真学校でも新学期がはじまって、一月、二月たつと学生たちの会話にやたら難しい言葉が入ってくる。被写界深度、相反則不軌、色温度、寛容度といった種類の技術的な用語と、マニピュレーテッド・フォトとかトポグラフィックスのような写真の表現や主義についての言葉だ。こんな言葉のなかで技術用語は写真を写すためには、知っていても知らなくても直接関係ないように思われる言葉だが、内容はいずれもよい写真を撮るためにはどうしても知っていないと困ることである。前回、スナップ撮影ではピントをいちいち合わせないで、レンズについているレバーの位置を動かすことでピントを合わせ写真を撮ることを話した。じつはこれが難しい言葉の一つである被写界深度に大変に関係があるのだ。レバーは本来これを動かしてレンジファインダーでピントを合わせるために付いている。でも使っているうちにレバーが真下にくれば2メートルのところにピントが合うことがわかる。だから2メートルのところを撮るときはいちいちレンジファインダーをのぞかなくても、そのまま写真を撮る。大変簡単なことである。まあーこういう順番になるのだが、本当はそんなことではない。ライカだってC型までは距離計がついていなかった。ライカだけではない、プレス用の大型ハンドカメラだって距離計はついていなかった。
前に朝日の出版写真部に入ったとき、スピグラ(スピード・グラフィック)を使わせられたと書いたが、スピグラまでの何ヶ月かの間「パルモス改造」というボロボロの大型ハンドカメラを練習用に使わさせられた。パルモスはスピグラ以前、つまり戦前の新聞社でアンゴーというキャビネサイズの大型カメラと並んで主力カメラであった。
カールツァイス社製と言うと格好がよいが、大正時代?(ひょっとしたら明治時代かもしれない)に製造されたもので、改造というのはフォーカルプレンシャッターをレンズシャッターに換えてあり、蛇腹のタスキがつないであった。ファインダーは簡単なフレーム式になっていて原型と大分ちがっているからだ。レンズはテッサー120ミリが着いていた。フィルムのサイズは手札版(手札判は9センチx12センチで4x5インチ判より一回り小さい)で、当然のことだが距離計(レンジファインダー)はついていない。
ピントを合わせる方法だが、一つはレンズシャッターを開放にしてフィルムホルダーをはずし、背面のピントグラス(フォーカスボード)をのぞいて焦点を合わせる。もう一つの方法は目測で計るかスケールで距離をはかり、レンズについている目盛りに合わせてレンズを前後に動かし距離を合わせる。このどちらかだ。ピントグラスで調節する方法は、カメラを三脚にでも乗せ、動かないものを撮るのには良いが、人間をはじめ多少とも動きのあるものを撮るのには向いていない。もともとハンドカメラは手持ちで撮影することを目的に造られているから、いちいちピントグラスをのぞいて撮るのには不便にできている。
クラシックカメラのことを書いてある本を調べてみると、パルモスはカール・ツアイス社のカメラ部門パルモス・バウからイカ(IKA)社に1907年引き継がれたと書いてある。イカ・パルモスの写真を見るとフォーカルシャッターの巻き上げノブが上部についている。私がつかったパルモスはノブが横に付いているからツアイス製だ。とすると1907年(明治40年)以前に製造されたことになる。ところがツアイス社のパルモスはレンズの焦点距離145ミリでイカ・パルモスはレンズの焦点距離120ミリとなっている。私が使ったパルモスには120ミリレンズが間違いなくついていたから、このへんがどうなったのかわからない。レンズボードを保持するタスキの金属がつないであったのは120ミリレンズを取り付けるために短くしたのかも知れない。
私が朝日に入る前から、写真部では新人を教育するのに、このパルモス改造を使い、目測で距離を計り写真を撮る練習をさせていたようだ。出版写真部に入った私は、しばらくはほかのカメラをつかってはいけないと命令された。この新人教育に協力してということではないのだろうが、同僚たちも何かにつけて「この机の端からむこうの電話まで何メートル何十何センチあるか」賭けようと挑戦をしかけてくる。賭けるのはコーヒーであったり、昼飯であったりなのだが、これが勝てないんですね、口惜しかった、先輩たちの目測の誤差はせいぜい1、2センチなのだ。あるとき食事を賭けてから、目標までの距離を巻き尺で計って見たら、私の誤差の方が少なくて、これは勝った万歳!と思ったら「俺は立っている。俺の目の位置から計れ」と言う。巻き尺できっちりと計ったら、その先輩の方が正確でがっかりしたことがあった。
パルモスを持って座談会の出席者の写真を撮りにいくことが多かった。撮影は料亭であったりホテルであったりした。この時、日本間であるとほっとした。理由は畳敷きだからだ、畳は幅3尺ときまっているから目測の目安が立てやすい。自信がないから何枚も撮る。帰ってきて暗室でフィルム現像ができるまでピントが合っているかどうか安心できなかった。
“パルモス改造”とは3ヶ月つき合った。3ヶ月つき合ったことで、目測で距離合わせができるようになった。だからこんなカメラを使わさせられて、などと思ったことはないし。ボロカメラだなどと思ったこともない。これは40年以上前、1950年代の話である。
カメラのオートフォーカスがどうだなどと言っている時代に、距離を目測で撮るなんて面白くもなんともないと思われるだろうが、今の時代でも、これが結構写真の表現には役に立つのだ。しかし、正確に目測で撮れると言っても、ピントが合う範囲はわずかだ。そこで被写界深度を利用することが必要になってくる。
被写界深度(ひしゃかいしんど)は、レンズに付いている絞り(ダイヤフラム)の働きによって生じてくる。絞りは本来、レンズという窓から入ってくる光の量を調節するカーテンの役目をするのだが、写真を撮っていてこのカーテンを開け閉めしているうちに、このカーテンがカメラに入ってくる光の量を調節するだけでなく、ちがう役目、働きをしていることに気がつくのだ。昔からレンズを作っている専門家たちはそんなことは充分、承知していたのだが、写真師といわれ写真家といわれる人たちは、実際に撮影をしていてこのことに気がついた。同じ距離にピントを合わせて絞りを絞っていくと、つまりレンズという窓のカーテンを閉めていくと、ピントが合ったように見える範囲が広がっていくのだ。人物を2メートルの距離で撮影していて、絞りが開いているよりも、閉まっているほうがピントが合ったように見える範囲がひろがるのなら、目測で距離を計って写真を撮るとき、多少間違っても、絞っていればピントが合ったようにみえる範囲が広がって助かることになる。