
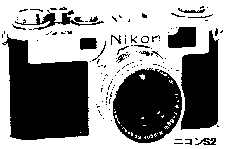 写真学校の授業のために、デジタルカメラで撮影した写真とリバーサルのカラーフィルムをデジタル化したものをプリンターで出力して教材につかうことが多くなってきた。はじめのうちは富士のピクトロ3000で出力してもらっていたが、最近はもっぱらインクジェットプリンターでプリントアウトして写真をつくっている。インクジェット方式のカラープリンターの発色が、想像できないくらい良くなってきたからである。プリント用紙がいろいろある。これを使って驚くのはプリントされた画像の色彩表現が紙によってあまりにも違いすぎることだ。いまデジタルフォトを実際に利用している人たちは、PCのモニター上で画像を見ることが大部分で、そんなことに頓着する必要がないのだろうが、いままで写真を職業にしていたものにとっては、どうしてもこだわらざるを得ないことである。これは、カメラ雑誌にもパソコン雑誌の製品紹介にも扱われていない盲点のような気がする。
写真学校の授業のために、デジタルカメラで撮影した写真とリバーサルのカラーフィルムをデジタル化したものをプリンターで出力して教材につかうことが多くなってきた。はじめのうちは富士のピクトロ3000で出力してもらっていたが、最近はもっぱらインクジェットプリンターでプリントアウトして写真をつくっている。インクジェット方式のカラープリンターの発色が、想像できないくらい良くなってきたからである。プリント用紙がいろいろある。これを使って驚くのはプリントされた画像の色彩表現が紙によってあまりにも違いすぎることだ。いまデジタルフォトを実際に利用している人たちは、PCのモニター上で画像を見ることが大部分で、そんなことに頓着する必要がないのだろうが、いままで写真を職業にしていたものにとっては、どうしてもこだわらざるを得ないことである。これは、カメラ雑誌にもパソコン雑誌の製品紹介にも扱われていない盲点のような気がする。
話は全く違うことなのだが、昔、ライフの写真家であった三木淳さん(故人)と話をしていたら、アメリカではカメラマンとはムービーカメラをまわす人、スチール写真を撮る人はフォトグラファーとはっきりしているが、日本ではいい加減だ。新聞社・雑誌社などで給料もらって写真をとっている人、アマチュアで写真を撮る人たちがカメラマンで、フリーで写真を撮るプロの人たちをフォトグラファー・写真家と言っている。この辺をはっきりしておかないと、いまになにがなんだかわからなくなってしまうといっていたが、確かに最近はこれがはっきりしなくなってきた。すこし名前がとおると写真家で、カメラマンはすこし低く見られるというおかしなことになっているようだ。だから自称写真家ばかりが目立っている。写真師とか写真士を名乗る人がでてきてもいいと思う。師には「教える人」の意味もあるが「技芸に優れた人、一つの技術を専門にする人」の意味があるそうだし、士などは漢和辞典を見ると「事を処理する能力のある者」と書いてあるから、ぴったりだと思うのですがね。
ジャーナリズムで仕事をするプロのカメラマン・写真家は、スタッフとフリーに分けられる。フリーというのは厳密には給料などで拘束されないと同時に、カメラも自前、フィルムも自分持ち、取材費も世話にならないが原則である。スタッフの場合は給料は当然、カメラ、フィルム会社持ち、そのかわり写真の著作権は当然のように雇用者に帰属してしまう。
私が朝日の出版写真部に入ったころ、会社の備品のカメラやレンズがあったがほとんどが戦前からの機材であったので、仕事には自分のカメラで取材撮影することの方がはるかに多かった。上司であった歴代の出版写真部長は雑誌ジャーナリズムで写真がしめる重要性についてよく理解している人たちだったので新しいカメラや機材をそろえるために、上司を説き伏せて予算をとろうとして努力したのだが、前例を盾にとられて機材の整備はなかなか進展しなかったらしい。特に小型カメラに関しては、新聞の写真部で使っていないものを、出版ではなぜ必要なのかと言われて、これを説得するために実際に雑誌に掲載された写真を例にあげて小型カメラと大型カメラの違いを説明したりしたのだがなかなかわかってもらえなかったようである。出版写真部員が工面をして自前のカメラを買って仕事につかっている窮状?を訴えたら、ある局長は「昔の武士は刀は自前であった」と武士の魂は自前が当然論をぶちあげたそうである。それが昭和30年代になって少しずつ変わってきた。理由はカラー写真の必要性が言われはじめたこと、写真の著作権論議が盛んになってきたこと、それになんと言ってもジャーナリズムの世界で現実に写真が伝えるインパクトの強さがはっきりと認められるようになって、どの雑誌もグラビア写真ページをふくめて写真の強化が必要になってきたことなどが重なっていた。新聞社ではカラー写真について必要性は感じていたが、まだ手をつけてはいなかった。カラー写真と言う新しい分野については、前例がないと言うお役所的な言い分がとおらなくなってきていた。著作権の問題は会社が雇用著作権を主張するためには、カメラなど機材を雇用者が用意しないと具合が悪いことになってきた。
個人的なことを言えば、朝日新聞社の給料はほかの企業にくらべて良かったようだし、給料のほかに支給される時間外手当が毎月給料と同じ額くらいあった。それに賞金稼ぎと言うとオーバーだけれど、カメラメーカーやいろいろな企業や団体が企画する写真コンテストなどに応募して入ってくる賞金があったりした。独身生活で余裕があったから、あまり気にしないでカメラを買うことができた。そんなことで会社の備品カメラが揃わなくても撮影に困るようなことはなかったし、あまり大事なことは思っていなかった。自分のカメラで撮るのが当たり前みたいな感じで仕事をしていた。
そんなころに突然、新品のニコンS2が1台支給されたのである。写真部に大幅の予算が増加が認められて、各部員に小型カメラ1台が支給されたのだ。カメラには35ミリレンズがついていた。一眼レフカメラ以前のことである。私は小型カメラはそれまでライカタイプのキヤノンIVsbとライカIIIcそれにニッカを主に使用していた。このごろはこれをバルナックタイプと言うんですね。そのころの詳しい事情はわからないが、朝日出版写真部としては備品のカメラを日本光学製のものにすることが決まったようである。先輩たちはキャノンにするかニコンにするか侃々諤々の大討論をしたようだ。私はニコンが嫌いだといういわけではなく、ライカとおなじタイプということだけでキヤノンをつかいはじめたわけだったから、新しいカメラがつかえることで、ただ単純に喜んでいたように思う。しかし、これはいろいろな意味でありがたかった。はじめにキヤノンを使い始めたことで、それに固執していたら、上っ面だけを見てカメラの長所も欠点も本当の意味では見えてこないし、カメラの本当の良さはわかってこない。ニコンS2をそのとき使わなかったなら、その後もS型ニコンを使うことはなかったと思う。
ニコンS2の良さはファインダーにあった。等倍の一眼式連動距離計がついていた。ニコンはキヤノンのIVsbに比べて連動距離計が見やすかったから、きちんと距離計で焦点を合わせて写真を撮るのがやさしかった。と言うとおかしなことを言っているように思われるかもしれないが、キヤノンをはじめライカタイプのカメラでスナップ撮影をするときは、レンズのレバーの位置で距離を確かめて撮影する方法をとっていたから距離計の見やすさをあまり問題にしていなかったのだ。ニコンS2のレンジファインダーを使って、ファインダー全体の見やすさに驚いた。これは後にM型ライカのファインダーではもっと驚かされることになるのだが、これでニコンも悪くないなーと食わず嫌いを反省することになる。
35ミリレンズが取材の常用レンズであった。このレンズをつけてレンジファインダーのカメラでキヤノンとニコンどちらを余計につかったかと考えてみると総量でキヤノンだが、ある時期に限ってみるとニコンに集中している。記憶がはっきりしないのだが、S2を会社から支給されてからしばらくはつかわなっかった。それはキヤノンをはじめライカタイプのカメラに慣れていたので使わなかったのだと思う。慣れないカメラを仕事にすぐ使うのにはためらいがあったからだ。
昭和30年代後半、東京オリンピックのころは、長い焦点のレンズはニコンF、広角と標準はニコンSという組み合わせがニュース写真などのの取材スタイルであった。S型ニコンはS2と、その後、自前で買ったS3の2台だけだ。を買っている。S3の発売はニコンFと同時期であった。ニコンSPというS型の最高級カメラが発売されたのは昭和32年で、これはミランダと同時期だったから、そのときはこの一眼レフに気をうばわれていたいて、高価なSPに対してはまったく興味がなっかった。
日本のレンジファインダー型のカメラはキヤノンはライカ、ニコンはコンタックスといずれもドイツ製のカメラを模倣したものだから、外見だけでなく機能の面でも似ていた。M型になってもライカは固執しているがフィルムをいれるためにあける底蓋(フタ)はカメラ本体とは離れてしまう。キヤノンのIVsbもそういであった。コンタックス、ニコンは裏蓋と底が一体になっていて、これも本体から離れてしまう。
そんなことはどうでもよいことのようだが、そうでもないのだ。昭和34年9月、死者五千人が出た伊勢湾台風の取材にいった。氾濫した木曽川流域の長島付近を自衛隊のボートに乗せてもらって撮影していた、狭いボートの上でフィルムを入れかえていた。ボートが流木にあたり、そのはずみで手をすべらせてキャノンの底蓋を水中に落としてしまった。あっと言う間もなっかった。予備のカメラを何台も持ち歩いていたからいいようなものの、ほかにカメラがなければ撮影はできなかった。このことは恥ずかしくて東京に帰ってからもしばらく言い出せなかった。その後、聞いてみると結構おなじ失敗をしているカメラマン・写真家がいるのですね。しかもこれはプロに多い。
私の友人に狂熱的なライカ信奉家がいる、彼によるとライカがいまだに底蓋分離方式を続けているのはカメラの精密度のためで、裏ブタ連結式ではボデにねじれが出て精度が悪くなり、レンズに対するフィルムの平行度がたもてないのだそうである。