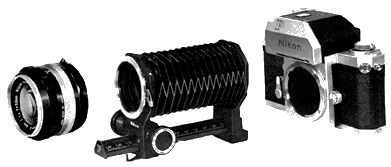 レンジファインダーカメラでは焦点が合っているのかどうかわからないし、ファインダーでは対象物が画面にどのくらい入っているかわからないから、ミラーボックスを利用せざるをえない。これでピントの問題は解決できるが、問題は露出である。
レンジファインダーカメラでは焦点が合っているのかどうかわからないし、ファインダーでは対象物が画面にどのくらい入っているかわからないから、ミラーボックスを利用せざるをえない。これでピントの問題は解決できるが、問題は露出である。
 秋山庄太郎さんは写真学校の卒業式で話されたが、今年、80歳なっての目標は花の写真で絵はがき1000枚をつくることだそうである。とにかく花の写真に熱中されていてご自分が主宰されている花の会が自慢で、よくこの花を撮影するグループのことが話題になる。
秋山庄太郎さんは写真学校の卒業式で話されたが、今年、80歳なっての目標は花の写真で絵はがき1000枚をつくることだそうである。とにかく花の写真に熱中されていてご自分が主宰されている花の会が自慢で、よくこの花を撮影するグループのことが話題になる。「こんなに花の写真に興味を持っている人が多いとは思わなかった。花の写真を撮る人がどんどん増えている。会のメンバーには年輩のご婦人が多い。年をとられた方もたくさんいる。それまで写真を撮った経験のない人がほとんどだが、これだけ花の写真を撮っている僕らが見ても、はっとするようなすばらしい写真を撮る。写真を知らなくても花を愛しているだけで写真は写る。カメラの進歩が花の写真を盛んにしたようだ」
まあーこんな内容のことを言われるのだが、小生の知人に花の会のメンバーがいる。この人は写真の大ベテランだ。秋山さんが言っていることは極端かも知れないが、そういうメンバーの人が多いということは事実だろう。
カメラの機能のことは何も知らない。ひたすらファインダーをのぞいてシャッターボタンを押す。オートカメラのおかげだ。この会のメンバーはほとんどが一眼レフカメラを使っている。花を接写する機会が多いからである。カメラのメカについてはまず何も知らない。
カラーフィルムを使うのだがフィルムの感度も知らない。シャッターがどんなものか、絞りのあることももちろん知らない。ファインダーをのぞいてシャッターボタンを押せば目に見えるとおり写ると信じている。
ほとんどがオート露出機構(プログラムシャッター)をつかっている。これでも花を撮って傑作は撮れるのである。カメラは道具なのだから、道具が進化したらその進化した道具を使えばよいのである。
私が朝日新聞社の出版写真部に入ったころは、雑誌はまだカラーページが少なくて、印刷も今から見れば大変に粗末な時代だったが、雑誌に関わりをもつものは、誰もがこれからはカラーの時代になるであろうことはわかっていた。だからカラー写真の研究は大なり小なり、どこの雑誌社のカメラマンでもやりはじめていた。こんな時代のことである。
接写撮影は難しかった。このごろはマクロ撮影というのが普通で、接写撮影というのはすこしばかり古いのかも知れない。科学朝日という朝日新聞社発行の月刊雑誌があった。戦争中に創刊された雑誌で、いまはサイアスと名前がかわっている。
朝日に入社して間もなく(昭和二九年)初めてこの雑誌の仕事をしたときカラーが1ページだけあった。いろいろなものをこのページはとりあげていた。図鑑的なものも多かったが、その時々の科学的な話題で写真が撮れるものはカラーで撮って紹介していた。このカラーページの仕事にマクロ・接写撮影が多かった。
接写には定義があって、至近距離から等倍撮影までをいっている。等倍撮影とは対象物と同じ大きさにフィルム上に写すことである。それ以上大きく写す場合は拡大撮影と言うのが本当らしいが、最近は等倍以上でも接写と言っているようである。
接写というのはご存じと思うが大型カメラの場合はカメラの蛇腹を伸ばして撮影する。35ミリカメラの場合はレンズとカメラボディの間に中間リングや延長用ベローズを入れてレンズとフィルム面の距離を広げて撮る。レンズとフィルム面の距離が伸びれば伸びるほど、対象物に近づき大きく写る。
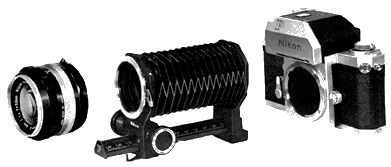 レンジファインダーカメラでは焦点が合っているのかどうかわからないし、ファインダーでは対象物が画面にどのくらい入っているかわからないから、ミラーボックスを利用せざるをえない。これでピントの問題は解決できるが、問題は露出である。
レンジファインダーカメラでは焦点が合っているのかどうかわからないし、ファインダーでは対象物が画面にどのくらい入っているかわからないから、ミラーボックスを利用せざるをえない。これでピントの問題は解決できるが、問題は露出である。
モノクロ撮影のときの露出はかなりいい加減でも、フィルム現像を含めて引き伸ばし焼き付け処理まで含めると寛容度(ラチチュード)が高いから何とか写ってくれる。多少の露出の過不足はフィルムがカバーしてくれる。わからないときはオーバー目に露光すれば、何とかなるよ、ですんでいたが、カラー撮影になるとそうはいかなくなってくる。
当時使用したカラーフィルムは感度ISO24のエクタクロームが主でコダクロームも平行して使っていた思う。このフィルムは露出が難しかった。わずかのオーバーでも色が飛んでしまうし、わずかなアンダーでも真っ黒になってなにが写っているのかわからなくなってしまう。一段階・1絞りのミスはとても許してもらえない。
風景や人物など普通の撮影でも露出が難しいのに、これが接写となるとレンズがフィルム面から離れる分を補正・加減しなければいけないことになる。露出計で計ったEv値(エックスポジュアバリュー)をそのまま使って撮影すると露出不足の写真になってしまう。
大型カメラではレンズの繰り出しによる露出倍数が繰り出しボードについていて計算してつかうことのできるカメラもあった。小型カメラでは拡大倍率を出し、これから露出倍数を計算して露出値を出して撮影した。いまではこの数式も忘れてしまったが、この計算した数値がきわめてあてにならなかった。
ほんのわずかカメラの位置が前後にずれると露出がどんどん変わっていった。なんどもテスト撮影をしてみて大体こんな露出でいいだろうと思って撮影をするのだが自信がもてない。恥ずかしい話だが、撮影の現場でこのときはフラッシュ撮影であったが、露出がわからなくなり迷って35ミリフィルム一本36枚全部を露出を1枚1枚変えて撮ったことがある。このとき数本のフィルムを使ったのだが、現像をしてみると、きっちりと露出があっていたのは5、6枚しかなかった。
学校で接写を教えていて、この恥ずかしい経験を話しても学生は何で、という顔をする。接写の露出で苦労するなど考えられないことだからである。TTLでフィルム面にあたる光量を正確に計ることが出来るからだ。
最近のカメラ雑誌をみていると、レンジファインダー・カメラを流行らせようとしているように見える。ベッサRが発売されたのが契機のようだが、先日も知り合いのカメラ店によったら、ニコンのS3の復刻版の予約を受け付けているが先生もどうですかっと聞かれた。S3は徹底的に使って傷だらけになったのを一台もっているから結構と断った。
その翌日、渋谷のカメラの量販店にいったらここでも大々的に予約を取っている。顔見知りの店員さんに「予約する人、たくさんいますか」ときいてみたら、人数は教えてくれなかったが結構多いんですと、言っていた。
流行するかどうか、たしかにレンジファインダー・カメラを使えばちがう写真が見えてくることも事実だが、これだけ一眼レフカメラが進んでしまうとレンジファインダー・カメラではできないことがあることに気がつく。接写撮影などはこれがはっきりしている。
でもこんな風になってきたのは、一度の急激に変わったのではなくて、いろいろなカメラが作られ、いろいろな段階を経て今のようになってきた。キヤノンのAE−1でもA−1でもある段階で新しい機能が加わり、これを教えてくれた大事なカメラと云うことが出来る。
写真(1)はキヤノンズームレンズの接写機能の目盛り。A−1で使ったズームレンズには、対象物からフィルム面30センチまで近づけ接写出来る機能がついていた。ズームレンズのヘリコイドを広角側35ミリよりさらにまわしM目盛りに固定すると接写ができた。現在の普及型一眼レフカメラについているズームレンズにはほとんど接写機能が付いていて、当たり前になっているが、考えてみるとキヤノンのこのレンズがこの機能を取り入れた最初のものかも知れない。
写真(2)これはニコンFの時代、接写の道具でベローズと言う延長チューブが売り出されていた。ベローズとは蛇腹のことで、当時、接写ではこれを使用するのが普通であった。このベローズにはベローズ・フォーカシング・アタッチメント・モデルIIIと商品名がついていた。